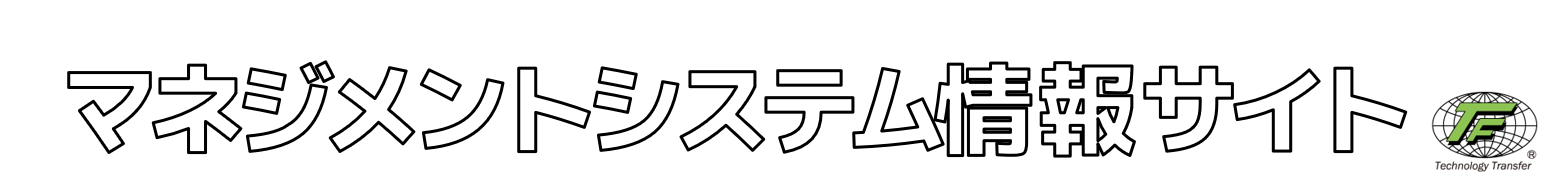こんにちは。ISO 14001講師の吉田宣幸です。
今回は、SDGsのISO文書を身近に感じていただきたく、ISO 14001との比較をしながら、類似性を中心に解説していきたいと思います。(※ISO 14001は、環境マネジメントシステムの規格)
そもそも国連SDGsには17の目標があり、例えば13番から15番が、気候変動、海の生態系、陸の生態系など、環境関連の目標が多数含まれています。
今年2024年9月に発行された「ISO/UNDP PAS 53002:2024」の正式名は、「Guidelines for contributing to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)」です。直訳すると、国連SDGsへの貢献のための指針(ガイドライン)です。
ISOとUNDP(国連開発計画)が協同で開発したため、頭の部分が「ISO/UNDP」となっています。ちなみに、UNDPは国連の機関で、環境問題や経済を含む社会的発展に寄与する活動を行っています。
「PAS」は公開仕様書(Publicly Available Specifications)を意味しており、国際規格に比べて短期間で開発できるメリットがあるため、今回採用されました。一刻も早くSDGsに貢献したい、という気持ちがにじみ出ています。
本文を見ると、助動詞は「shall」ではなく「should」等が書かれています。これは、準拠が必須ではなく、準拠することが望ましいということであり、要求事項ではなく指針(ガイドライン)という位置づけのためです。
目次を見ると、箇条番号のズレはありますが、ISO 14001とほとんど同じ順番になっています。
箇条4には、ISO 14001の4.1に該当する内容が書いてあります(4.1 組織及びその状況の理解)。
外部の課題、内部の課題の例示がされています。「先住民族や地元の知識を考慮」などのフレーズもあり、より広くとらえることが推奨されています。
※ここからは「箇条」や「細分箇条」と書いた場合は「ISO/UNDP PAS 53002:2024」を指し、単に「4」や「4.1」などと記載する場合は「ISO 14001:2015/Amd.1:2024」を指します。
箇条5には、ISO 14001の4.2に該当する内容が書いてあります(4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解)。
「利害関係者」を「SDGsへの貢献を最適化することに関係する利害関係者(原文は『the interested parties relevant to optimizing its contributions to the SDGs』」としていますので、ISO14001と同様に受ける側と与える側の両方が該当します。
細分箇条5.2には、SDGs影響を受ける側の例示がされています。
細分箇条5.3には、SDGs影響を与える側の例示がされています。
なお、SDGs影響には、良い影響と悪い影響の両方の意味が含まれています。
箇条6には、ISO 14001の4.3と4.4などに関係する内容が書いてありますが、より的確には5.1等いろいろな箇所に記載されている『事業プロセスとの統合』に該当することが書かれています。(4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定、4.4 環境マネジメントシステム)。
「SDG活動のコアビジネスへの統合(原文は『Integration of SDG activities into core business』)」が重要です。
細分箇条7.1には、ISO 14001の5.1に該当する内容が書いてあります(5.1 リーダーシップ及びコミットメント)。
細分箇条7.2には、原則(Principles)が書かれており、敢えて言えば、ISO 14001の5.2やISO 9001の0.2に該当する内容が書いてあります(5.2 環境方針)(0.2 品質マネジメントの原則)。
「悪影響に対して影響を受けた利害関係者に補償する方法を計画する」等が、原則の一つである「accountability(説明を伴う責任)」に含まれています。
原則には、次の7つがあります。
a) 説明責任 (accountability)
b) 透明性 (transparency)
c) 倫理的行動(ethical behaviour)
d) 利害関係者のニーズと期待の尊重(respect for interested parties’ needs and expectations)
e) 国際行動規範の尊重(respect for international norms of behaviour)
f) 人権の尊重(respect for human rights)
g) 誰一人取り残さない(leave no one behind)
最後の『leave no one behind』は、世間では「LNOB」と記載されることもあり、SDGsをよくご存知の方には、お馴染みのフレーズ『No one will be left behind』のことです。
(直訳すると「誰も取り残さない」ですが、外務省の訳語に合わせて、置き去りにしない旨を強調する「誰一人取り残さない」と書きました)
細分箇条7.3には、ISO 14001の10.1、10.3に該当する内容が書いてあります(10 改善 10.1 一般、10.3 継続的改善)。
イノベーション(Innovation)には、科学技術の革新だけでなく、ビジネスモデルやデータ収集、分析、普及におけるイノベーションなど様々なことがあり得ます。
細分箇条7.4.2には、ISO 14001の7.4(コミュニケーション)よりも強い内容が書かれており、ISO 45001の5.4(5.4 働く人の協議及び参加)に該当する内容が書いてあります。
タイトルの「協議と参加のプロセス(原文では『Processes for consultation and participation』)」とは、利害関係者の協議と参加のためのプロセスのことで、意思決定前にいろいろな意見交換をすることと、意思決定に加わること(例えば、投票する)の両方を指しています。
細分箇条7.4.3には、ISO 14001の7.4や8.1など複数の箇所に該当する内容が書いてあります。
利害関係者との協業や協力を推奨しています。
タイトルは『Collaboration and partnerships』(コラボレーションとパートナーシップ)です。
箇条8には、ISO 14001の5.2に該当する内容が書いてあります(5.2 環境方針)。
箇条9には、ISO 14001の5.3に該当する内容が書いてあります(5.3 組織の役割,責任及び権限)。
細分箇条10.1には、ISO 14001の6.1に該当する内容が書いてあります(6.1 リスク及び機会への取組み)。
細分箇条10.2には、ISO 14001の6.1.3に該当する内容が書いてあります(6.1.3 順守義務)。
細分箇条10.3には、ISO 14001の6.2に該当する内容が書いてあります(6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定)。
細分箇条10.4には、ISO 14001の8.1に該当する内容が書いてあります(8.1 運用の計画及び管理)が、むしろISO 9001の6.3(6.3 変更の計画)に該当すると言った方が的確です。ちなみにISO14001の改訂で、将来6.3が入る可能性が高いため、その時点では整合すると思います。
箇条11には、ISO 14001の7に該当する内容が書いてあります(7 支援)。
細分箇条12.1には、ISO 14001の8.1に該当する内容が書いてあります(8.1 運用の計画及び管理)。
細分箇条12.2には、ISO 14001の8.1に該当する内容が書いてあります(8.1 運用の計画及び管理)が、タイトルは『Externally provided processes, products and services』(外部から提供されるプロセス、製品、サービス)ですので、むしろISO9001の8.4(ISO 9001 8.4 外部から提供されるプロセス,製品及びサービスの管理)の方がしっくりきますね。
細分箇条12.3には、ISO 14001の9.1や6.1.2に該当する内容が書いてあります(9.1 監視,測定,分析及び評価、6.1.2 環境側面)。
細分箇条12.4には、ISO 14001の6.1.2や6.1.4に該当する内容が書いてあります(6.1.2 環境側面、6.1.4 取組みの計画策定)。
なお、優先順位付けについては、ISO 45001で管理策の優先順位を「8.1.2 危険源の除去及び労働安全衛生リスクの低減」に決めていますので、その決定判断のプロセスを自社内で構築しているようでしたら、システム構築の際に参考にできるかもしれません。
細分箇条13.1には、ISO 14001の9.1に該当する内容が書いてあります(9.1 監視,測定,分析及び評価)。
細分箇条13.2には、ISO 14001の9.2に該当する内容が書いてあります(9.2 内部監査)。
細分箇条13.3には、ISO 14001の9.3に該当する内容が書いてあります(9.3 マネジメントレビュー)。
細分箇条14.1には、ISO 14001の10.1や10.3に該当する内容が書いてあります(10 改善 10.1 一般、10.3 継続的改善)。
細分箇条14.2には、ISO 14001の10.2に該当する内容が書いてあります(10.2 不適合及び是正処置)。
いかがでしょうか。ISO 14001との類似性をお話ししましたので、皆さんにとってはより身近に感じていただけたのではないでしょうか。
違いの部分ももちろんたくさんありますが、ガイドライン(指針)ですので気楽に、取り入れやすい部分から採用し始めてはいかがでしょうか。