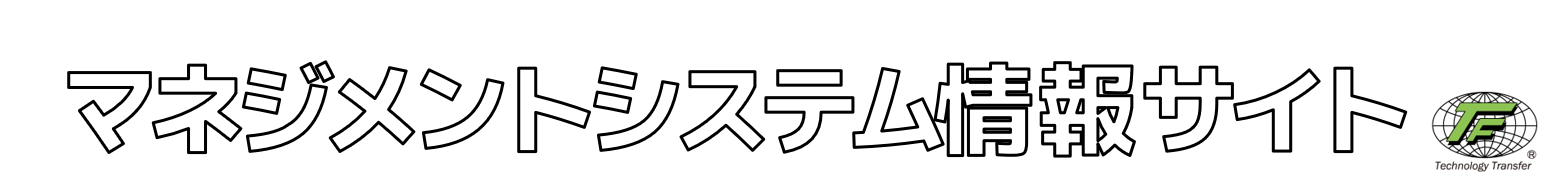このコラムでは、ISO 9001、ISO 14001 の審査や研修講師に長年従事してきた氏による、ISO を取り巻く様々な課題について感じていることを語っていただいています。 この記事は、テクノファNEWS(2022年11月号)に掲載した記事です。 はじめに データ不正は、数年前大きな社会問題となり、様々な指摘、その原因の議論が行われた。しかし、大手電機、トラック・バス製造の自動車と不正事件は不死鳥のごとく繰り返し発生している。組織がなぜ他社事例に学んで組織内点検や、悪しき伝統を断てないのであろうか。 不正横行の原因は、デロイトトーマツグループによるアンケート調査結果によれば、「業績等を優先する組織風土」が51%、次いで「人事固定化」、「上司の指示が絶対」、「事なかれ主義」、「コミュニケーション不全」がそれぞれ35%前後という(回答数476社、複数回答)[1]。ここから、不正の要因別に私見を述べたいと思う。 1.業績等を優先する組織風土 小職も5,6年前に品質不正問題が世間をにぎわしたとき、日本の組織風土として閉鎖的な村意識に基づく自組織の都合と利益優先を指
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。